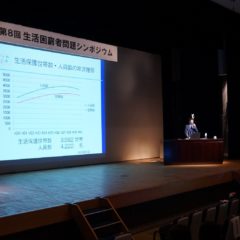見えない生きづらさに寄り添う支援を探る 福井でシンポジウム

「生きづらいと感じていても相談先や居場所が見つからない」。自ら声を上げることができない女性や子どもたちをどのようにして支援につなげるかを考える「第15回済生会生活困窮者問題シンポジウム」が10月18日に福井県済生会病院で開かれ、地域住民や福祉関係者ら約200人が参加しました。
午後1時に、炭谷茂・済生会理事長と鷲頭美央・福井県済生会会長(福井県副知事)が開会あいさつ。登谷大修・福井県済生会支部長が趣旨説明をしました。
始めに厚労省社会保障審議会の委員も務める橋本達昌・社会的養育地域支援ネットワーク代表理事が「生きづらさを抱える若い女性や子どもたちを地域で支えるために私たちができること」と題し講演、「現代社会では親子関係や地域社会との”つながりの貧困”の問題もある。地域共生社会の実現には専門家のケア(支援)、地域住民のチア(応援)、当事者市民のピア(支え)の三つ連携が重要で、行政はこれらを活動を支える存在であるべき」と語りました。
その後のパネルディスカッションでは橋本氏がコーディネーターを務め、それぞれの立場で支援する4人が取り組みを発表しました。
藤原美由紀・福井県健康福祉部児童家庭課長は県内に6カ所整備されている児童家庭支援センターについて、地域の専門相談窓口として住民などからの相談に応じて助言していることを説明しました。
児童養護施設で育ち現在は同施設で職員として働く板谷ゆりさんは当事者としての体験談を語り、短大生活でリズムが崩れ施設職員と距離を置いた時期もあったが変わらず寄り添ってくれた経験から、支援は制度だけでなく社会全体で見守っていく形が大切と話しました。
福井県で自立援助ホームや子どもシェルターを運営する一般社団法人ラシーヌの端 将一郎代表理事は繁華街の巡回やネットパトロールなどのアウトリーチも行ない家に帰りづらいなどの事情を抱える子どもたちへの支援活動を紹介しました。
2014年4月に開設した性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」の取り組みを発表した福井県済生会病院 公認心理師・臨床心理士の車屋知美さんは性暴力は心と体だけでなく行動面や生活面にも影響が及ぶと解説、「ひなぎく」では支援看護師の資格を持つ看護師が警察や弁腰と連携して相談者を支援していると説明しました。
その後、シンポジストと会場参加者とのディスカッションが行なわれ、最後に笠原善郎・福井県済生会病院院長があいさつをして閉会しました。
済生会本部広報課長 河内淳史


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス



_ページ_1-400x400.jpg)