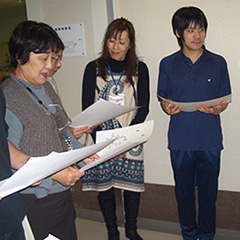広がりつつあるDCAT
3月11日、災害時に介護職員が出動するDCATを編成している山形県東村山郡山辺町の済生会特別養護老人ホーム やまのべ荘で、大規模災害に備えた防災訓練が行われました。
保護観察対象者が介護体験 利用者さんと交流
山口地域ケアセンター在宅複合型施設やすらぎで、昨年11月から1月にかけて5回にわたり、保護観察中の人たちがボランティアで介護の仕事に従事しました。
今年のインフルエンザは「A香港型」「H1N1pdm型」が混合
例年、インフルエンザの流行のピークは、1月第4週・第5週ごろ。国立感染症研究所が全国の薬局で患者さんを調査している「薬局サーベイランス」によると、1月13日~19日の推定患者数は39万人にのぼります。
ノロウイルスが流行 嘔吐・下痢の後始末に注意
毎年、冬になると増える感染性胃腸炎。その多くは、ノロウイルスへの感染が原因だと言われています。中津病院臨床教育部長・感染管理室室長の安井良則先生に、その対策を伺いました。
新しい済生丸が初の瀬戸内海巡回に
昨年進水した新しい診療船「済生丸」が1月15日、岡山県笠岡市・北木島で建造後初めての巡回診療に就きました。初検診は骨密度測定が主で、高齢者の方15人が受診し、結果をもとに医師の指導を受けました。
がん患者さんの就労支援を、ハローワークと連携して
がんは、今や不治の病ではありません。治療をしながら、十分、仕事や日常生活を続けていくことができるようになりつつあります。しかし一方で、従来通り働けなくなり、離職に追い込まれる方や、病気を職場に隠し、無理して働いている方も少なくありません。
フィリピン台風被害への緊急医療支援
2013年11月8日に、猛烈な台風30号が、フィリピン・レイテ島北東部の海岸にあるタクロバンを襲いました。死者は少なくとも5,000人を突破し、行方不明者1,700人以上に上る甚大な被害を出しました。
熊本病院が世界基準のJCI認証 西日本の病院で初 !
済生会熊本病院が、医療の質と安全において世界標準を満たすことを示す、米国の国際的医療機能評価機関(JCI)の認証を取得しました。


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス