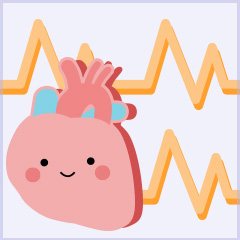2013.02.01 公開
2025.06.30 更新
拡張型心筋症
Cardiomyopathy
監修:髙橋 寿由樹 (東京都済生会中央病院 循環器内科 担当部長)
拡張型心筋症はこんな病気
拡張型心筋症は、心臓の筋肉がうまく収縮できなくなり、左心室が拡張する心筋症の一つです。この病気が進行すると、心不全や不整脈を引き起こす可能性があります。国内では約2万人の患者さんがいるとされていますが、症状に気づかず病院を受診していない方を含めると、実際の患者数はさらに多いと考えられます。
原因はまだ完全には解明されていませんが、ウイルス性心筋炎がきっかけとなる場合が多いと言われています。他にも、免疫異常や遺伝が関係している可能性があります。
ウイルス性心筋炎とは、風邪の原因となるウィルスが心臓に感染することで起こる病気です。風邪などをひいて約1週間後に突然、胸の苦しさや息苦しさを感じることがあっても、半数は風邪が治ると回復します。ただ、一部の方は慢性的に進行して、最終的に拡張型心筋症になる場合もあります。また、拡張型心筋症になっても症状が出にくいことがあり、診断されないケースも少なくありません。
拡張型心筋症の診断
胸部X線像では心臓の拡大が見られ、心電図にはさまざまな異常所見が現れます。心エコー検査では、心室壁の動きの低下も認められます。
心臓にストレスがかかったときなどに、心臓からホルモンの一種であるBNPが出てきます。BNPを測定することで心臓の状態を知ることができます。
なお、拡張型心筋症の診断は、虚血性心筋疾患などの特定心筋疾患による心筋異常を除外して行なわれます。また心臓カテーテル検査で心臓の動きを調べ、確定診断を行ないます。さらに、心筋生検で組織像を調べて原因を解明することもあります。
拡張型心筋症の治療
拡張型心筋症の治療法には、塩分制限に加えて、薬物療法と非薬物療法があります。心不全に対しては薬物療法が行なわれます。β遮断薬が有効であることがわかっており、多くの患者さんに投与されています。また、ACE阻害薬やアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬も改善効果が認められ、β遮断薬と併用して使われています。水分が貯留するケースでは、利尿薬が使われます。
また近年、糖尿病の薬として開発されたSGLT2阻害薬は、心不全にも有効であることがわかり、他の薬と併用して使われています。
不整脈を合併する重症な患者さんには、不整脈の薬剤が処方されます。薬以外の治療法には、再同期療法というペースメーカーを使った治療法があります。心臓の収縮が均一でない場合にペースメーカーを使って心臓の右側と左側が同時に収縮するようにします。また、不整脈による突然死を予防する目的で植え込み型除細動器が使われることもあります。
早期発見のポイント
拡張型心筋症を早期に発見するためには、次のような症状に注意することが重要です。
また、健康診断や人間ドックなどを受けた際に、心電図やX線検査で心臓の異常が見つかることがあります。
拡張型心筋症は初期段階でさまざまな症状が現れますが、特に多いのは息切れです。心臓から全身に血液を送り出すポンプ機能が低下すると、肺や体内で血液の流れが滞り、うっ血が起こります。その結果、例えば坂道や階段を上るときに、息切れを感じるようになります。この症状は、最初は運動時のみ現れますが、進行するにつれ、安静時や睡眠中にも呼吸困難を感じることがあります。
足や顔のむくみも、拡張型心筋症ではしばしば見られます。
呼吸困難、むくみはどちらも心不全の症状です。心不全は、心臓のポンプとしての機能が低下するために、身体のいろいろなところに「水」がたまります。足に溜まればむくみとして現れ、肺に溜まれば息切れなどとして現れます。初期の段階では、息切れがしても運動不足だと思ったり、咳き込んだりしても風邪だと勘違いすることがあるようです。なお、むくみは心臓だけでなく腎臓、肝臓の病気でも見られることがあります。
拡張型心筋症では、不整脈が現れることがあります。不整脈によって動悸を感じるほか、致死性心室性不整脈が起こると失神や、ときには突然死に至る場合があります。収縮力が低下した心臓では、血流が悪くなって血栓ができやすくなります。血栓が脳に流れていって脳血管が詰まり、脳梗塞になる危険性もあります。
拡張型心筋症の予後
拡張型心筋症は慢性的に進行することが多く、心不全による入院を繰り返したり、不整脈で突然死をきたすことがあります。欧米では心移植が必要となるケースが増えていると言われています。わが国では心移植適応例の80%以上が拡張型心筋症です。その一方で、近年の治療法の進歩もあり、5年生存率は80%へと改善しています。

監修:髙橋 寿由樹
東京都済生会中央病院
循環器内科 担当部長
※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス