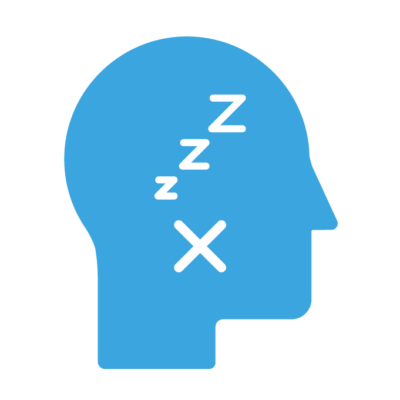 不眠
不眠
この症状が現れる主な病気 11件
不眠とは、必要な睡眠時間を確保できない(睡眠不足)だけでなく、睡眠の充足感が得られず、身体的・精神的・社会的な支障(昼間の疲労感やだるさなど)が出ている状態を指します。全人口の約1/3が一生のうちどこかの時点で不眠症にかかるといわれます。
下記のような症状が週2~3回以上、1カ月以上にわたって続いているときは医療機関(睡眠障害外来、精神科、内科など)を受診して相談しましょう。
- 入眠障害:なかなか寝付けない
- 中途覚醒:夜中に何回も目覚めてしまう
- 早朝覚醒:早い時間に起きてしまい、二度寝できない
- 熟睡障害:十分な睡眠時間をとっているのに、熟睡した感じがしない
不眠の原因は多岐にわたります。
多くの場合は、不眠の背景に病気があります。病気の治療薬(抗パーキンソン薬、降圧薬、喘息薬など)が不眠の原因になることもあります。また、いわゆる睡眠導入剤に対する依存症のような状態になっていることもあります。
睡眠障害を引き起こす病気には、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)、睡眠時周期性四肢運動障害、概日リズム睡眠障害などがあります。その他、慢性的な疼痛や、精神疾患が原因の場合もあり、それぞれの原因により違った対応・対策が必要です。
どんな人に、どんなときに現れるか
前述のように、多くの人が不眠を体験しますが、一般的には年齢が高くなるほど不眠を自覚する人が増えるといわれています。
また、子どもにも不眠は起こります。睡眠を妨げるような環境(過剰な昼寝、不規則な生活、就寝前のゲームやスマホなど)によるものや、しつけ不足(親の生活、社会的要因)によるもの、手のかかる特別な寝かしつけをしないと寝られないものなどがあります。
不眠の適切な治療のためには、どんな症状が出ていて、原因として何があり得るのかを知ることが大事です。後述のチェックポイントを参考に、受診前に確認しておくと診療の役に立ちます。
どんな病気が関係しているか
「不眠」の症状が現れる主な病気の中で、発症頻度の高いもの、特徴的なもの、注意が必要なものをとりあげました。病気についてさらに知りたい場合はリンク先をご参照ください。
|
症状とその特徴 |
説明 |
疑われる主な病気 |
|---|---|---|
|
・意欲や興味、食欲の低下 ・頭がぼーっとする ・身体の痛みや重さ |
こころの症状がほぼ毎日、2週間以上続き、生活に支障をきたす。身体の症状が出ることもある
|
|
|
・みぞおちの痛み、不快感 ・胸やけ、げっぷ ・黒色便 |
ピロリ菌感染や鎮痛剤などにより、粘膜に潰瘍ができて痛む |
|
|
・頻尿 ・尿意切迫感 ・トイレに間に合わない |
膀胱が過敏になっていて、尿をためにくくなる。夜間頻尿により中途覚醒 |
前立腺肥大症(男性) |
|
・息切れ ・動悸 ・疲れやすい、だるい |
心臓の病気によりポンプ機能が障害され、十分な血液が身体を巡らない |
|
|
・かゆみ ・発疹などは出ない |
高齢者では皮膚の乾燥で起こりやすい。腎臓や肝臓、糖尿病などの病気によるものもある |
チェックポイント
(1)次のような症状の有無を確認する
- どのような不眠の症状が出ているか
- 睡眠・覚醒リズム(起きていた時間、寝床にいた時間、睡眠していた時間、昼寝の時間)の確認
- 起床時の眠気はあるか、眠気はどの程度か
- 夜間、尿意を感じてトイレに行った回数
※「睡眠日誌」を利用してこれらを確認すると診療に役立ちます - 寝ているときに気になる症状(激しいいびき、呼吸停止、手足のむずむず感や動きなど)があるか
※睡眠を共にする方がいれば様子を教えてもらってください - 睡眠に関係すること以外で気になる症状があるか
(2)次のような環境を確認する
- 精神的なストレスを抱えていないか
- 現在、患っている病気はあるか
- 健康診断などで異常を指摘されていないか
- 飲んでいる薬やサプリメントの種類
- 寝る前に酒やたばこ、カフェインをとっていないか
- 寝る前にスマホやパソコン、テレビを見る習慣はないか
- 寝室の温度や湿度、照明、寝具は適切か
- 運動習慣はあるか
- 海外渡航や生活の大きな変化があったか

解説:泉 学
済生会宇都宮病院
内科系診療部長補佐・総合診療科 主任診療科長
※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス












