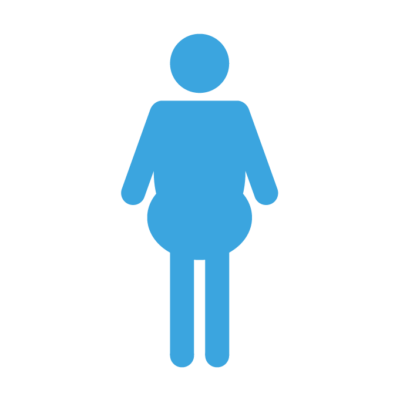 体重増加
体重増加
体重増加の原因として最も多いのは、食べ過ぎ(エネルギーの過剰摂取)による「肥満(原発性肥満)」です。肥満とは脂肪組織が体に過剰に蓄積した状態で、医学的にみて減量治療を必要とする肥満を「肥満症」と呼んでいます。多くは、過食に加え、運動不足、睡眠不足などの不適切な生活習慣をベースに、体質などの要因も関与して、徐々に体重が増加したものです。
肥満(特に内臓脂肪型肥満)があると、脂質代謝異常や糖代謝異常、高血圧、脂肪肝などを生じやすく、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの生命に関わる病気を発症するリスクが高まることが知られています。
生活習慣がベースとなって起こる「肥満」が大多数を占める一方で、何らかの病気が原因で体重増加(肥満)が起こることもあります。これを「二次性肥満(または症候性肥満)」といい、体重増加の原因となっている病気の治療が必要となる場合があります。
食事の量はそれほど多くないのに体重増加がみられたり、短期間に急激に体重が増加したり、あるいは体重増加に伴ってほかの症状も出現しているなどの場合には、一度内科を受診することをお勧めします。
どんな人に、どんなときに現れるか
主に内臓脂肪が蓄積するタイプの肥満(内臓脂肪型肥満)は中高年の男性に多くみられ、ウエスト周囲径の膨大が特徴です。一方、主に皮下に脂肪が蓄積するタイプの肥満(皮下脂肪型肥満)は女性に多くみられ、特にお尻や太ももなどに皮下脂肪がつき、下半身型(洋ナシ型)の肥満を呈します。
病気が原因で起こる体重増加(二次性肥満)がみられる代表的な病気には、甲状腺機能低下症やクッシング病といった内分泌疾患、腎不全や心不全、ネフローゼ症候群などがあります。急性の体重増加は、身体に水分が過剰に貯留する「むくみ(浮腫)」が直接的な原因であることが多くあります。
また、このほかに薬剤(副腎皮質ステロイドや向精神薬、経口避妊薬など)の影響で体重増加が起こることもあります。
どんな病気が関係しているか
「体重増加」の症状が現れる主な病気の中で、発症頻度の高いもの、特徴的なもの、注意が必要なものをとりあげました。病気についてさらに知りたい場合はリンク先をご参照ください。
|
症状とその特徴 |
説明 |
疑われる主な病気 |
|---|---|---|
|
・食欲不振 ・便秘 ・疲れやすい、寒がり ・皮膚の乾燥 ・徐脈 ・むくみ ・甲状腺(首前部)の腫れ |
女性に多い。甲状腺ホルモンの作用不足によって全身の代謝が低下し、むくみを伴って体重が増加する |
|
|
・顔が丸くなる(満月様顔貌) ・にきび ・皮下出血 ・高血圧 ・高血糖 ・精神症状(抑うつ) |
副腎皮質ホルモンの過剰分泌の影響で顔が丸くなったり、手足は細いのに腹部を中心に丸く太って体重が増加する |
クッシング病 |
|
・息切れ ・頻脈 ・血圧低下(または上昇) ・むくみ |
心機能の低下に伴う体循環のうっ滞により、四肢末梢を中心にむくみ、体重が増加する |
|
|
・貧血 ・高血圧 ・尿量の変化 ・むくみ ・息切れ |
腎機能の低下に伴う体液過剰により、全身性のむくみが現れ、体重が増加する |
|
|
・黄疸 ・腹部膨満 ・むくみ ・低アルブミン血症 |
肝臓の機能低下により、血中のアルブミンが低下する。腹水により腹部膨満となることもある |
|
|
・タンパク尿 ・むくみ ・高コレステロール血症 ・低アルブミン血症 |
尿中にアルブミンを含むタンパクが失われることにより、むくみが強くなる状態 |
チェックポイント
(1)次のような症状の有無を確認する
- 短期間に急激に体重が増加したか
- 体重増加以外に気になる症状があるか(あるならどのような症状か)
- 食欲が異常に強くなったり、なくなったりしていないか
- 体型に変化はないか(部分的に太った、むくんでいるなど)
- 息苦しくなったりしないか
(2)次のような環境を確認する
- 最近の食事量や内容に変化はなかったか
- 太るような食事に心当たりはないか(間食や外食は増えていないか)
- ストレスなどで過食気味になっていないか
- 運動不足や睡眠不足、不規則な生活などが続いていないか

解説:泉 学
済生会宇都宮病院
内科系診療部長補佐・総合診療科 主任診療科長
※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス













