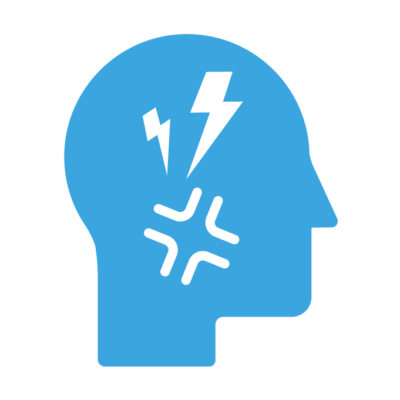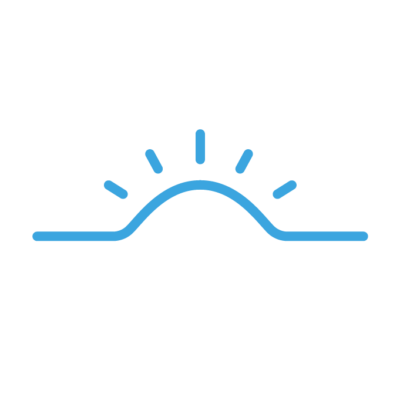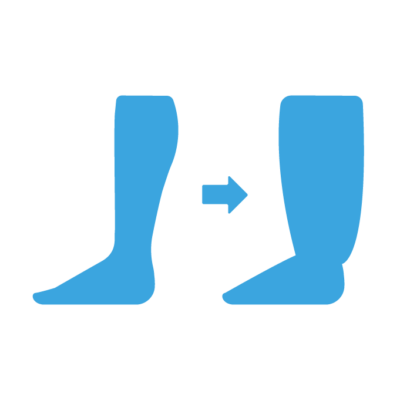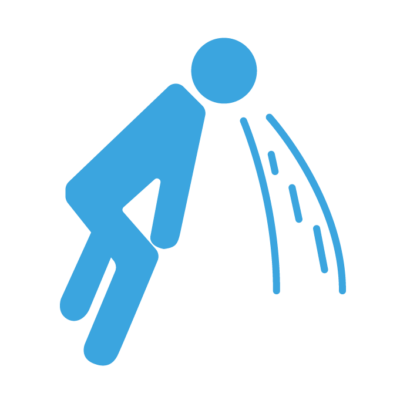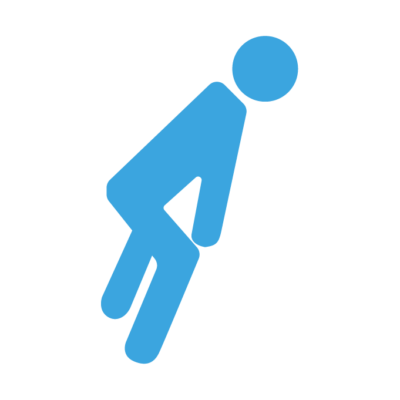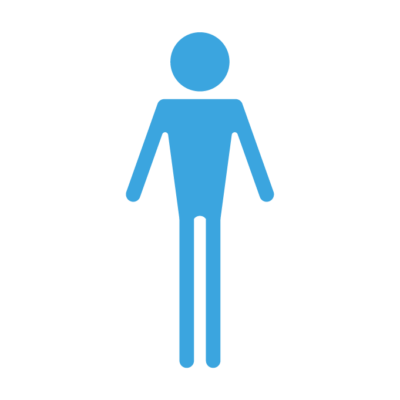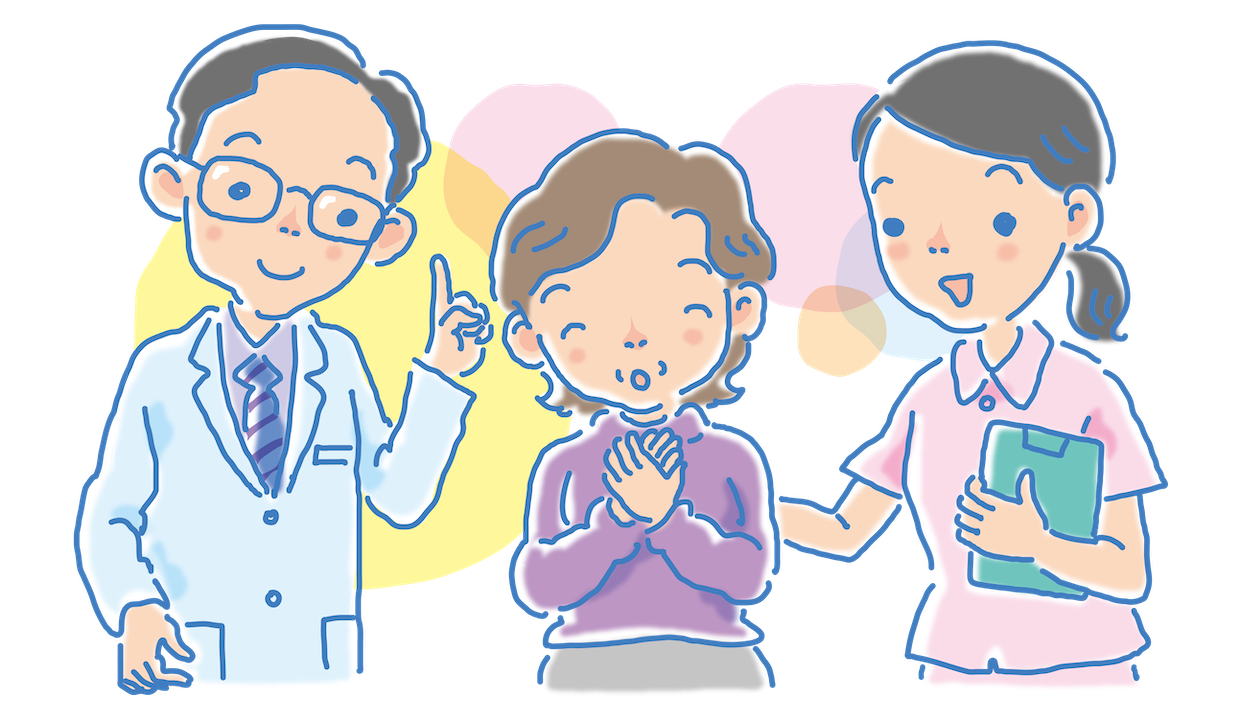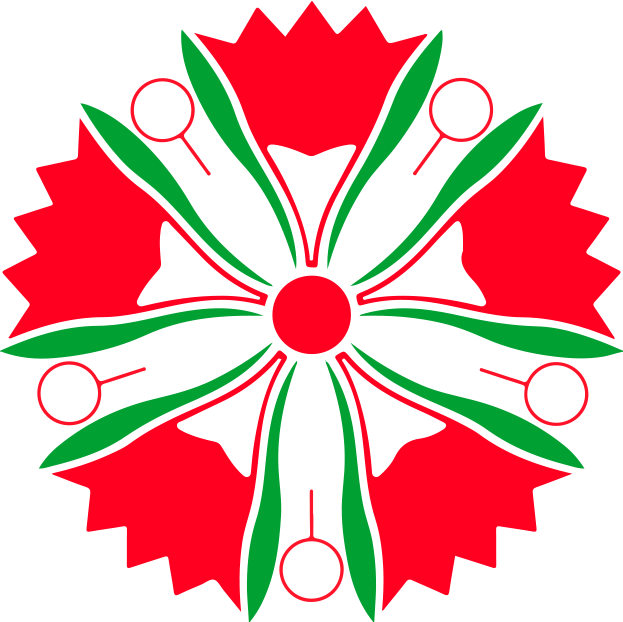2021.08.18 公開
小児がん(子どものがん)
childhood cancer
解説:伊藤 暢宏 (済生会長崎病院 小児科部長)
小児がんとは
小児がんは0~14歳の子どもにみられるがんの総称で、厳密には「小児がん」という特定の病気はありません。
主なものとして、白血病(血液のがん)、脳腫瘍、悪性リンパ腫、胚細胞腫瘍、神経芽腫があります。このうち白血病が38%と小児がんで最も多く、次いで脳腫瘍16%、リンパ腫9%、胚細胞腫瘍8%、神経芽腫7%となっています(国立がん研究センターがん情報サービス「小児・AYA世代のがん罹患」より)。
■白血病:主な症状は、貧血、出血、発熱、頭痛、嘔吐などです。
■脳腫瘍:頭痛や吐き気、不機嫌などのほか、意識障害や手足の麻痺などさまざまな症状が現れます。
■悪性リンパ腫:首や脇の下、足のつけ根などリンパ節の多いところに腫れ、痛みのないしこりが現れるほか、発熱や寝汗、体重減少などがみられます。
■胚細胞腫瘍:腫瘍がある部位によって症状は異なり、精巣や卵巣に発生した場合は腫瘤(こぶ)が生じます。
■神経芽腫:初期はほとんどが無症状ですが、進行するとお腹に腫れや硬いしこりができる場合があります。
小児がんの罹患率は子どもの人口1万人当たり約1人と、成人のがんに比べて低いです。成人のがんは生活習慣が原因となるものが多いですが、小児がんの原因は成長・発達の過程で発生した異常な細胞の増殖と考えられ、網膜芽細胞腫(眼のがん)など一部遺伝するものもあります。
また、小児がんはしっかりと治療すれば7~8割が治るといわれています。
小児がんの検査・診断
小児がんは、何らかの症状によって病院を受診したときや健康診断などをきっかけに見つかるケースが多いです。
診断には、CTやMRIといった画像検査や、血液検査などが必要になります。その結果小児がんが疑われる場合は、大学病院などの小児血液・がん専門医がいる施設でさらに検査を行ない診断することが多いです。がんの種類によっては、小児がん中央機関を通じて、より正確な診断が必要になることもあります。
小児がんの治療法
がんの種類や広がりによって治療方針は異なりますが、集学的治療が基本です。集学的治療とは、外科療法(手術による腫瘍摘出など)、化学療法(抗がん剤による治療)、放射線療法などを組み合わせて治療を行なうことです。そのため小児がんの治療は、小児科医だけではなく、外科医や放射線科医と連携して行ないます。
治療後は安心して生活できるように、外来診療でのフォローアップを長期的に行なうことが重要です。治療の合併症などで成長・発達に問題が出てくる場合もあります。治療が終了した後も、成長の各段階での医療のサポートが重要です。
小児がん治療の環境整備
2012年6月に閣議決定した「がん対策推進基本計画(第2期)」では、小児がん対策の基本計画として、小児がん患者さんとその家族が安心して適切な医療や支援を受けられる環境整備を目指し、全国で小児がんの中核的な機関の整備を開始することが目標に定められました。
これを受けて、2013年2月に全国15カ所の「小児がん拠点病院」を指定。翌年2月には全国の小児がん拠点病院をけん引する「小児がん中央機関」として、国立成育医療研究センターと国立がん研究センターの2カ所を指定しました。患者さんは地域の特性に合わせて専門医がいる施設で高度な医療を受けることが推奨されています。
がんの種類や部位などによって現れる症状はさまざまです。
一部を挙げると、発熱、体重減少、疲労感、不機嫌、食欲低下、原因不明の痛み、嘔吐を伴う頭痛、首周辺のリンパ節の腫れ、息苦しさ、顔のむくみといった症状がみられます。
変化に気づきにくいため、後から振り返ってみると上記の症状に思い当たるといったケースが多いです。気になる症状が続く場合はかかりつけ医に相談しましょう。
小児がんは成長・発達の過程で発生した異常な細胞の増殖や、遺伝が原因となるため、未然に防ぐのは難しいです。「早期発見のポイント」で記載している症状がみられる場合は、速やかに医療機関を受診してください。

解説:伊藤 暢宏
済生会長崎病院
小児科部長
※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス