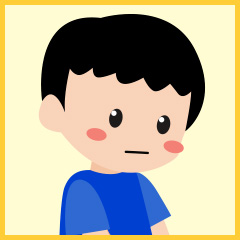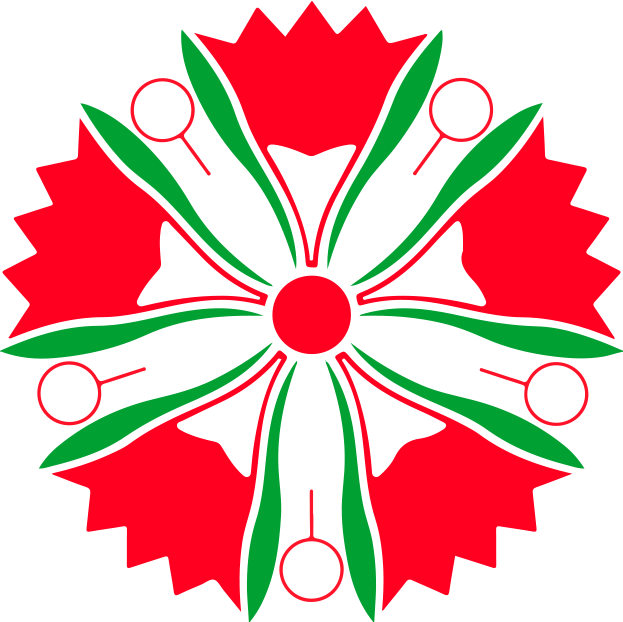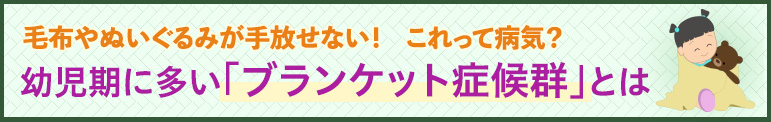
「子どもがお気に入りの毛布やぬいぐるみを手放さないけど大丈夫?」──。そんな悩みをお持ちの親御さんは少なくないのではないでしょうか。こうした状態は主に幼児期にみられ、「ブランケット症候群」と呼ばれます。特徴や原因のほか向き合い方などを常陸大宮済生会病院・小児科部長の鏑木(かぶらき)陽一郎先生に聞きました。
ブランケット症候群を知っていますか?
●『スヌーピー』の男の子ライナスのように
ブランケット症候群の定義は、「特定のアイテム(いちばん多くみられるのが毛布やぬいぐるみなど布系のもの)を持つことで、精神的な安心感を保っている状態」とされます。
漫画『スヌーピー』に登場する、いつでも青い毛布を引きずっている男の子ライナスのようなイメージといえば分かりやすいでしょうか? 実際、ブランケット症候群は「ライナスの毛布」や「安心毛布」とも呼ばれています。
また、心理学の分野では毛布やぬいぐるみなどの「特定のアイテム」のことを「移行対象」といいます。
●よくみられる年齢や男女比は?
ブランケット症候群は年齢を問わず、生後5、6カ月以降の離乳食が始まる頃から成人まで幅広くみられますが、中でも幼児期によく現れます。
男女比については女の子の方が多いという研究報告が多いです。その理由は、手にする特定のアイテム(移行対象)がぬいぐるみなどになることが多いため、女の子は親和性が高くなりやすいためではないかと推測されます。
●病気ではありません
症候群という呼び名に不安を覚える人もいるかもしれません。しかし、ブランケット症候群自体は病気ではありません。
「移行対象」という語を提唱したイギリスの小児科医で精神分析医のD・W・ウィニコットの論文の中に「移行対象は、ほどよい母親*1と乳児の間に生まれる産物である」という記述があります。つまり、適切な育児の中で生じるのが移行対象であり、ブランケット症候群は健全な成長過程の一部といえます。
*1:「ほどよい母親」とは、ほどほどの距離感で子どもと接する母親を指す。新生児の頃は子どもの欲求にすべて応じていたのが、成長とともに徐々に関わりを弱め、適度な距離感で世話をするようになること。

欧米の子どもは移行対象に依存しやすい?
欧米では早期から子どもの自立を促すことが多く、スパッと授乳を打ち切ったり、必要以上のスキンシップを取らず本人に行動を促したりする傾向があるため、子どもが移行対象に頼る割合が高くなるという指摘があります。逆にアジア圏では、日本や中国のおんぶ文化など子育ての中でスキンシップを取ることが多いことから、移行対象に依存する割合が欧米に比べて低くなるようです。その意味で、ブランケット症候群は欧米の方が比較的多くみられるといえるかもしれません。
ブランケット症候群がみられる背景
●子どもの発達に伴う移行期間
子どもは授乳時の乳房などを通じて、母親に対して同一性や一体性を持つとされます。こうした「私とママは一心同体」の状態から、離乳食が始まる生後5、6カ月頃を境に徐々に母子の同一性が弱まっていきます。
とはいえ、子どもはすぐに母親との同一性を捨てきれず、同一性を想起させるものがないと不安になります。その結果、なんらかの移行対象を求めるようになります。
つまり、ブランケット症候群がみられる背景には「母親から離れることへの不安感」があると考えられます。見方を変えると、子どもが自立に向けてのスタート地点に立っている状態と捉えることもできるでしょう。

●親の愛情不足と関連性はない
ブランケット症候群がみられるのは、親の愛情不足が原因ではないかと不安に思う人もいるかもしれません。しかし、ブランケット症候群と親の愛情不足との関連性は一概に説明ができません。先述の通り、ブランケット症候群は健全な成長過程の一部とすれば、愛情の量とは無関係と考えてよいでしょう。
ブランケット症候群にどう向き合う?
●基本は「見守る」こと
ブランケット症候群に対する基本的な向き合い方としては、過度に心配したり、移行対象を無理に取り上げたりせずに、「見守る」ことです。子どもが5、6歳頃になって、多少は社会性が身についてくれば、「こういう場所(場面)では使わないようにしようね」と約束をすることで折り合いをつけるのも一つの方法でしょう。
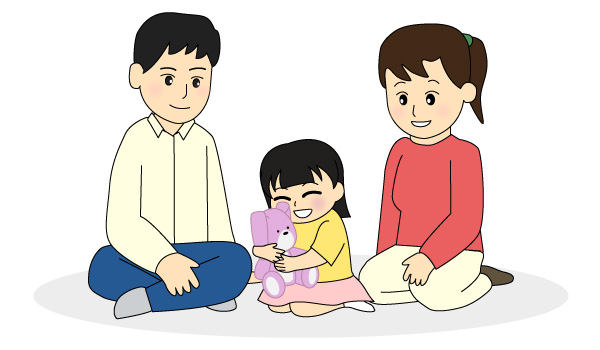
●「自宅だけ」か「自宅以外でも」が判断基準の一つ
ぬいぐるみなど一つの対象に子どもが強く執着するために、「分離不安障害*2」や発達障害の「自閉スペクトラム症」ではないかと周囲が心配する人もいます。
ブランケット症候群とこれらの障害を見分ける際、執着が自宅のみか、自宅以外でもみられるかが一つの判断ポイントとなります。何歳以降と明確には言いにくいのですが、ある程度世間体を気にする年齢になっても、学校など公共の場所でも移行対象に執着するような場合は、小児科などへの相談を検討してみてもよいでしょう。
逆に、自宅では移行対象を手放せなくても、友だちの前や公共の空間では恥ずかしがって持たなくなるような状態は、正常な発達の範囲と考えられます。同様に、成人以降も移行対象を手放せないケースはありますが、その場合も、周囲の人に迷惑をかけずに日常生活を送れているならさほど心配はいりません。
先に述べたように、ブランケット症候群は病気ではなく、成長の一つの過程です。家族や周囲の人は、心配しすぎず、まずは見守るようにしましょう。
*2:親(通常は母親)など愛着を持っている存在から離れることを極度に恐れる障害。分離不安症とも呼ばれる。

解説:鏑木 陽一郎
常陸大宮済生会病院
小児科部長
※所属・役職は本ページ公開当時のものです。異動等により変わる場合もありますので、ご了承ください。
※診断・治療を必要とする方は最寄りの医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
関連記事
病気解説特集
- 今年も暑い夏が到来! 熱中症対策に有効な「暑熱順化」を知っていますか? 2025.07.03
- せきや痰が長引く場合は要注意! 国内で急増中の「肺MAC症」とは? 2025.06.18
- 雨の日に頭痛や動悸、倦怠感…それって「気象病」かも? 知っておきたい予防法と対策 2025.05.21
- 正しく知ろう! 子宮頸がんを予防する 「HPVワクチン」ってどんなもの? 2025.04.15
- 休日は元気だけど、仕事になると気分が落ち込む 「非定型うつ病」の実態と対処法 2025.03.26
- そのアクションが命を救う! 私たちにもできる救命救急のキホン 2025.03.05
- なんとなく受けてはいるけど…… 実はあまり知られていない健康診断の常識 2025.01.31
- ヒートショック、低体温、生活習慣病悪化…… 高齢者が気を付けたい 冬の健康管理 2024.12.27
- 変異株やワクチンなど……この冬に知りたい 新型コロナの最新事情 Q&A 2024.11.29
- 子どもの食物アレルギーを怖がり過ぎないで! 「食物経口負荷試験」で正しく知ろう 2024.10.31
- すべて見る


 済生会の理念
済生会の理念 施設と拠点
施設と拠点 症状別病気解説
症状別病気解説 お知らせ
お知らせ
 採用情報
採用情報 トピックス
トピックス