

- 済生会について
- 事業内容
 事業内容
事業内容済生会は、403施設・435事業を運営し、64,000人が働く、日本最大の社会福祉法人です。全国の施設が連携し、ソーシャルインクルージョンの推進、最新の医療による地域貢献、医療と福祉のシームレスなサービス提供などに取り組んでいます。
- 施設と拠点
- 症状別病気解説
 症状別病気解説
症状別病気解説主な症状やからだの部位・特徴、キーワード、病名から病気を調べることができます。症状ごとにその原因やメカニズム、関連する病気などを紹介し、それぞれの病気について早期発見のポイント、予防の基礎知識などを専門医が解説します。
- お知らせ
- 採用情報
 採用情報
採用情報全国の済生会では初期臨床研修医・専攻医・常勤医師、看護師、専門職、事務職や看護学生を募集しています。医療・保健・福祉にかかわる幅広い領域において、地域に密着した現場で活躍できます。
- トピックス
 トピックス
トピックス一般の方の心身の健康や暮らしの役に立つ情報を発信中。「症状別病気解説」をはじめとして、特集記事や家族で楽しめる動画など、さまざまなコンテンツを展開しています。
- 寄付のお願い
- English
-
冬場に注意 低温やけど
寒くなるにつれ、こたつや使い捨てカイロで暖を取る機会が増えてきました。ここで注意したいのが、暖房器具による低温やけどです。高温でのやけどと違いじわじわとダメージを受けるため、気づかないうちに重症化することも。済生会吉備病院・形成外科の永瀬洋先生に、冬場に気をつけたい低温やけどについて聞きました。
大人に知ってほしい。子どもだって頭痛がつらい!
自分の子どもや生徒が頭痛を訴えたとき「どうせ仮病でしょ」「熱がないなら大丈夫」などと思っていないでしょうか。中には大人に理解されないまま、痛みで学校に行けなくなるほど苦しんでいる子もいるのです。福井県済生会病院で小・中学生のための「こどもの頭痛外来」を担当する小児科主任部長・岩井和之先生に、大人が知っておくべき子どもの頭痛について聞きました。
「フレイル」は介護予防のキーワード 普段の食事と運動が大事
「フレイル」という言葉を聞いたことはありますか? まだあまりなじみのない医学用語ですが、加齢によって心身が衰えた状態のことをいいます。年をとれば当たり前と考えられてきたこの状態は、早く気づいて適切な対策を行なえば回復する可能性があります。御所病院の志野佳秀副院長(消化器外科)に、フレイルの対策・予防のポイントについて解説していただきます。
正しく知ろう!骨髄を提供する「ドナー」になるために
血液の病気を治療するために行なわれる骨髄移植。現在も、骨髄バンクを介して約2,000人の患者さんが必要としています。若い世代のドナー登録が必要ですが、骨髄移植と聞いて「すごく痛い」といったネガティブな印象を持つ人も少なくないようです。骨髄のしくみや骨髄移植、骨髄提供の現状について解説します。
嚥下について知っていますか?若いうちから対策を!
嚥下(えんげ)障害は、何らかの原因で飲み込みにくい状態になることを指し、高齢になるほど起こりやすくなります。嚥下障害を起こすと、栄養不足に陥ったり、食べ物が気道に入って肺炎を起こしたりと、深刻な影響が出る可能性があります。若いころからどのようなことに注意したらよいか、和歌山県済生会有田病院副院長でリハビリセンター長の角谷直彦先生にアドバイスしてもらいます。
虫・植物を甘く見るのはキケン!夏のレジャーに出かける前に徹底した対策を
いよいよ夏も本番、アウトドアを楽しむ季節になりました。みなさんは虫刺されや植物による皮膚のかぶれの対策は万全ですか? たかが虫刺されだと甘く見ていると、命にかかわる場合があります。今回は、大阪府済生会泉尾病院・皮膚科医長の倉澤友輔先生に、アウトドアで気をつけるべき虫・植物や、対策のポイントなどを解説していただきます。
男性のがん患者さんの悩みを解決する方法
がんの罹患数は女性よりも男性が多い一方で、がんサロンに参加する患者さんは女性が大半を占めています。自分のことを話すのが苦手で、あまり他者と交流したがらない男性が少なくないためかもしれません。それゆえ、社会から切り離され、ふさぎ込んでしまうこともあります。そこで、がんサロンで男性限定の時間「男学」を設けている石川県済生会金沢病院の龍澤泰彦副院長に、がんにかかった男性の現状とその解決策について、お話を伺いました。
病院嫌いにさせない!子どものためにできること
病院が嫌いな子どもには、痛いことよりも何をされるのか分からないことが怖い子どもが多いといいます。子どもの不安を軽減するために大人は何ができるのでしょうか。医療を受ける子どもを”遊び”で支援するホスピタルプレイスペシャリスト(HPS)である、静岡済生会総合病院の望月ます美さんに、子どもの不安を取り除く方法を解説していただきます。
飲みすぎ注意!急性アルコール中毒・予防のススメ
4月は歓迎会など宴会が多い時期で、急性アルコール中毒で搬送されたというニュースを毎年耳にします。最悪の場合死に至ることもある急性アルコール中毒、お酒に強い体質であるか否かは関係ありません。済生会宇都宮病院の救急・集中治療科(ERチーム)の藤井公一先生が、その危険性やお酒を飲むときの注意点を解説します。
海外旅行へ行く前に! 渡航先に合わせて病気の対策を
今年のゴールデンウイークは10連休。海外旅行を検討している人にとって、渡航先で注意すべき病気は気になるところ。そんなとき、海外へ行く前に情報収集と対策を行なうには、病院の「渡航前外来」を活用しましょう。今回は、鹿児島病院の渡航前外来を担当する、久保園高明先生に、旅行などで渡航する際に注意すべき病気と、渡航前に取るべき対策を聞きました。
病気解説特集
- 男性の「乳がん」をご存じですか? 2024.03.22
- 肉を食べる際は要注意! 「ステーキハウス症候群」とは? 2024.02.22
- 過度なダイエットは危険⁉ 胎児にも影響を及ぼす「痩せ」の健康リスク 2024.01.29
- 急な温度変化で鼻がムズムズ それ「寒暖差アレルギー」かもしれません 2023.12.25
- 本当は怖い「新型タバコ」 電子タバコと加熱式タバコの影響とは? 2023.11.24
- 若い世代で増加中? 「スマホ急性内斜視」に要注意! 2023.10.24
- 気づいたら親が「セルフ・ネグレクト」に? 「孤立死」や「ごみ屋敷」に至る前に対策を 2023.09.26
- 走れ! ドクターカー いち早く救急現場に出動して命をつなぐ 2023.08.21
- 子どもだけじゃない! 気をつけよう「大人の食物アレルギー」 2023.07.31
- ちゃんといいウンチ出てる? 知って得するウンチの話 2023.06.23
- すべて見る
 施設と拠点
施設と拠点 お知らせ
お知らせ

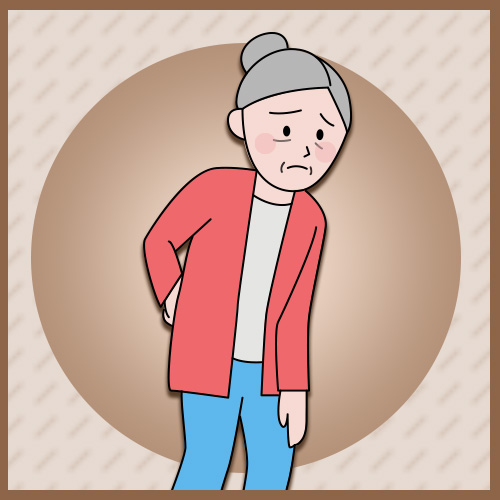









 済生会共同治験ネットワーク
済生会共同治験ネットワーク この人
この人 済生春秋
済生春秋 薬剤師が教える薬のキホン
薬剤師が教える薬のキホン いまいみさの魔法のおりがみ
いまいみさの魔法のおりがみ

 済生会保健・医療・福祉総合研究所
済生会保健・医療・福祉総合研究所